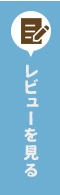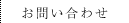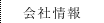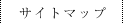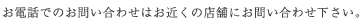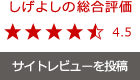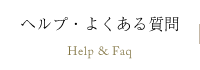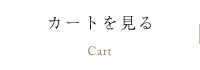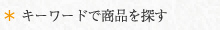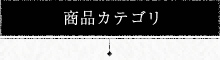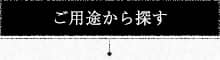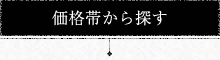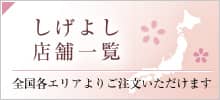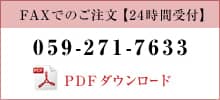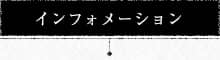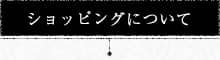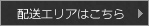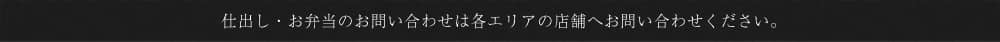■11月15日は七五三。平安時代から続く、子どもの成長を祝う行事

七五三は、毎年11月15日。子どもが無事に成長したことをお祝いする家庭行事のひとつで、
3歳の女の子、5歳の男の子、7歳の女の子が家族と共に神社にお参りする習わしがあります。
■七五三の由来
七五三の由来は、室町時代にまでさかのぼります。
当時は、幼児の死亡率が今では想像できないほど高かったため、生まれてから3、4年経って初めて、戸籍に登録されました。
死亡率の高い危険な幼児期を乗り越え、無事に成長することは、決して当たり前のことではありませんでした。
そこで、戸籍の登録が無事できる年齢まで成長できたことを、子どもの生まれた土地の神様に感謝し、今後の成長についての加護を祈る儀式が行われるようになりました。
平安時代になると、3歳、5歳、7歳になったことを祝う儀式が行われるようになります。
3歳の儀式は「髪置の儀(かみおきのぎ)」です。3歳になると、病気にかかりにくいように剃っていた髪を伸ばし始めたため、無事髪をのばせる歳になったお祝いという意味です。
5歳の男児の儀式は、「袴着の儀(はかまぎのぎ)」です。男児は、5歳で初めて袴を身につけるので、この名がつけられました。
7歳の女児の儀式は、「帯解の儀(おびときのぎ)」です。女児は、7歳になると、着物を着る際、紐ではなく帯を結ぶようになったため、このように名が付けられました。
こうした儀式は、宮中や公家といったごく一部の特権階層の儀式でしたが、江戸時代になると、武家や裕福な商人たちの間でもおこなわれるようになり、同時に、呉服屋が儀式を庶民にも宣伝し、一般的に広く行われるようになりました。子どもの成長を喜び、健康を願うのは、時代を問わず、親に共通する気持ちです。この儀式があっという間に広まったのも頷けます。
明治時代になると、これらの3つの儀式をまとめて「七五三」と呼ぶようになり、現在の七五三へと受け継がれています。
面白いことに、今も、由来となった儀式の意味がそのまま反映されています。
3歳の七五三では、まだきちんとした帯を結びません。きちとした帯は、7歳で結ぶからです。幼児用の紐付きの着物に兵児帯などを簡単に結んでいるだけなので、被布という袖なしの羽織りものを着用します。
5歳の七五三では、「袴着」という言葉通りに、紋付の羽織袴を着用します。
7歳では、「帯解き」という言葉通りに、華やかな振袖に袋帯や丸帯を締めます。お着物に紐が付いていないのは、大人と同じように帯を締めますので、着付けも大人同様、腰ひもを用いて着付けるためです。
■七五三の日取り
本来、七五三の日取りは11月15日でしたが、今では、この日に限らず、10月~11月の良き日を選んでなさるご家族も多いようです。
七五三が11月15日となった理由には諸説ありますが、有力だといわれている説をご紹介致します。
三代将軍・徳川家光の子供である後の5代将軍・綱吉は病弱だったといわれています。家光は、わが子の健康を案じ、「袴着の儀式」の際、綱吉の健康を願うお祈りをしてもらうことにしました。
大事な日を選ぶにあたり、二十八宿(地球を中心として取り巻く、天の赤道を28のエリア(星宿)に分割したという考え方)で、最もめでたい日とされている鬼宿日(きしゅくにち)であること、また、月が満ちる日でもあるということから、15日が選ばれました。また、11月は、旧暦で十二支がはじまる重要な月であることから、11月15日にしたようです。
鬼宿日は、なんだか恐ろしい日のように感じますが、鬼が宿に居て、外には出ないという意味で、鬼がいない安全な日とされました。
綱吉がその後、元気に育ったことから、この日を七五三をお祝いする日としたとされています。
■千歳飴の由来とは?

七五三のお祝いをした子供たちの手には、大事そうに千歳飴が握られていますよね。
この千歳飴の由来も諸説ありますが、以下の二つが有力なようです。
江戸時代、飴売りの七兵衛が、浅草で紅白の細長い飴を売り歩いたのが始まりとする説。
1615年ごろ、大阪の商人であった平野甚左衛門が江戸に出てきて、浅草の境内で「長い飴を食べると千年でも長生きするよ」と紅白の細長い飴を売り始めたのが最初とする説。
どちらも、当時は、長寿を連想させる千年飴と呼ばれていたと言われています。千年飴が転じて千歳飴となったようです。
当時は甘いものが大変貴重だったので、この千年飴は子供たちにとって、格別な贈り物であったことが想像できますね。
細長い形状も、名前同様、長寿をイメージさせます。この形状は今でも守られており、千歳飴は、直径15mm位、長さ1m以内と決められています。伝統を守る日本人ならではの決まり事ですね。
飴を入れる袋には、「鶴は千年、亀は万年」と言われるように、長生きを象徴する鶴亀、「冬でも緑を保つ松竹、冬を耐えて真っ先に花を咲かせる梅」として健康や生命力の象徴とされる松竹梅などが描かれています。
おめでたいことを表す漢字「寿」の文字も入り、健康な成長を願う縁起物となりました。
七五三の歴史を紐解くと、いつの時代も子どもの成長を切に願う親の気持ちが詰まった行事だということが身に染みてわかります。
七五三を迎えられるお子様がいらっしゃるご家庭では、是非お子様に、七五三の由来をお話しながら、成長を喜ぶ気持ちを沢山伝えてさしあげて下さい。七五三は、お子様のよき思い出となると共に、成長をいつも願ってくれる親の愛情を思い出す行事となるに違いありません。
七五三を迎えられたお子様の姿を見かけるだけでも幸せな気持ちになるのは、七五三がかくも愛情に満ち溢れた儀式だからなのですね。
今年も、沢山の可愛らしい姿を見かける時期になりました。すべてのお子様が、幸せに、健康で成長されますように祈念しております。
■七五三を祝う食事の楽しみ方

七五三のお祝いに、食事会を開く家庭も多いことでしょう。
その際のポイントを紹介します。
●お店で食事をするなら個室を予約
お店で食事をするなら、周りを気にしなくてすむ個室のある店を選びましょう。写真撮影や神社への参拝の前後に行くのであれば、その近くのお店が便利です。お店で食事をする家庭は和食を選ぶケースが多く、パパ、ママ、子どもに加え、祖父母をよぶ場合もあるようです
●仕出し弁当を頼み、自宅で祝うのもおすすめ
赤ちゃんがいるなどで、外で食事をゆっくり楽しめないという場合は、仕出し弁当などを頼み、自宅で食事をするのもよいでしょう。時期的に、七五三にまつわるメニューがあるお店もありますので、事前に調べて予約しましょう。
●着物の汚れを防ぐため、着替えを持参する
着物のまま食事をしても問題ありませんが、子どもの場合は動きにくくてぐずったりすることが
あるのに加え、こぼして汚してしまうこともあります。着替えを持参するか、着物のまま食べるのであれば、大きめのエプロンなどを準備しておきましょう。
各家庭のベストな日を選んで、子どもの健やかな成長をお祝いしましょう。