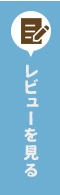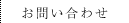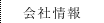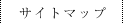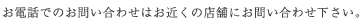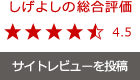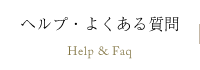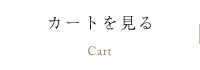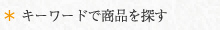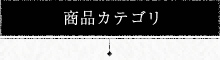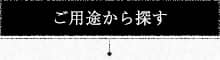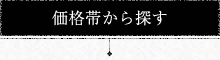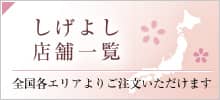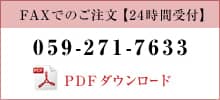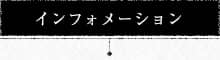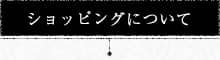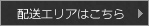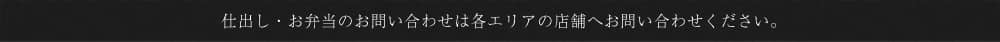2018/04/08

【食材のこだわり】たけのこ【しげよし】春の味覚といえば、筍。炊きこみご飯や煮物など、食卓に素敵な香りを添えてくれます。今回は、筍についてご紹介いたします。
■最もポピュラーなのは「孟宗竹」の筍です
たけのこの語源は「竹の子」。その名のとおり、竹の若芽が筍です。漢字の筍は、たけかんむりに「旬」と書きます。漢字の「旬」とは上旬、中旬、下旬というように10日間を意味します。たけのこは約10日で成長するため、たけかんむりが付いた「筍」が、竹の若芽を指す漢字になりました。 竹はイネ科で、最もよく見かける筍は、中国から渡来した孟宗竹(モウソウチク)の若芽です。 孟宗竹は、中国三国時代の呉に実在した人物「孟宗」にちなんだ竹です。孟宗は大変、母親孝行な人で、筍好きな母のため、筍が採れる季節ではない冬に竹林に入り、筍を母に食べさせたいと祈ったそうです。すると筍が生えてきて、母に食べさせることができたという故事にちなみ、孟宗竹の名が付きました。 日本には遣唐使として派遣された道雄上人が、帰国後に勅命を受けて京都の長岡に広大な敷地の海印寺を建立した際、その裏山に唐の孟宗竹を植えたことで広まりました。約1200年前の弘仁年間(810から823年)に伝来したと伝えられています。 孟宗竹の筍は大きくて厚みがあり、実が白くて柔らかいのが特徴です。また、えぐみが少なくて甘みがあるので、和食ととても相性がいいです。 いわゆる「京たけのこ」は孟宗竹です。高品質な京たけのこを生産するために、冬期にたけのこ畑一面にワラを敷き、その上に土入れをします。大変な手間がかかりますが、こうすることで白く、刺身ができるほど柔らかく、独特の甘味と香りが高い「京たけのこ」に育つのです。「京たけのこ」は早堀りで3月中旬から下旬、最盛期は4月中旬から5月上旬頃です。
■筍は縁起のいい食材です
筍は10日で竹になるほど成長が早く、天を貫くようにまっすぐに伸びていき、次々に群生することから、「成長」「立身出世」「家運伸長と繁栄」を象徴する食材として、おせち料理や端午の節句のお料理などによく使われます。 筍と相性がいい食材は、ちょうど同じく旬を迎えるサンショウの葉。先日のブログでもご紹介させていただきました。割った筍の先に山椒味噌を付けると、大変美味しゅうございます。
和食に欠かせないたけのこは、中国で生まれたイネ科の植物。国内の温暖が地域に多く生えており、その種類は70ほど。
■低カロリーで栄養価が高いたけのこ。白いブツブツは食べられるの?
たけのこは、ゆでると100gあたり30キロカロリー、市販の水煮缶詰は、100gあたり23キロカリーと、とても低カロリーの食品です。
■料理の前にアク抜きが必要な理由
たけのこは、収穫直後からアクが増し、食べる時にえぐみが出てしまいます。手に入れたら、なるべく早く、丸ごとゆでましょう。 筍を皮ごとゆでるのは、皮に筍を柔らかくしてくれる成分が含まれているからです。また、米ぬかに含まれるカルシウムには、筍のえぐみの元であるシュウ酸やホモゲンチジン酸などを中和する作用があり、アクとえぐみがよく取れます。鷹の爪には、ピリッとした風味でえぐみを和らげたり、ぬか臭さを抑えたり、防腐効果を高めたりする役割があります。 保存するときは、茹でた筍を冷水と鷹の爪とともに保存容器に入れて、冷蔵庫で保管してください。なるべく早めにお召し上がりいただくのがおすすめです。
|