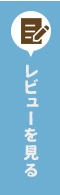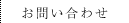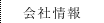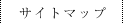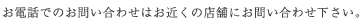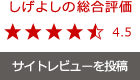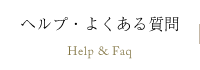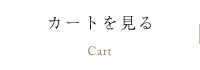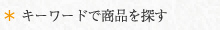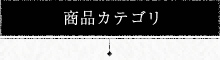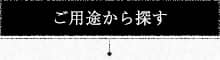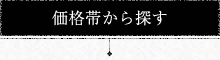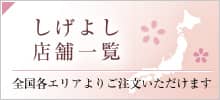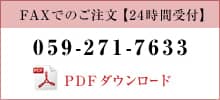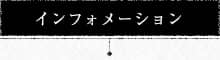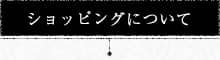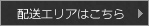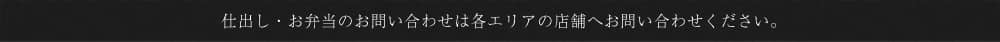■冬至とは

二十四節気のひとつでもある「冬至」とは、1年で最も昼間の時間が短くなる日。
冬至の日はいえば、「太陽の力がいちばん弱まる日」といえますが、この日を境に太陽の力は再び蘇っていき、昼間の時間が少しずつ長くなっていきます。
昔の人々は、冬至の日を「一陽来服(いちようらいふく)の日」とよび、太陽の復活を祝っていました。
「冬至を境に運も上昇する」と考えられているので、長期保存できるかぼちゃを食べて栄養をつけ、体を温めるゆず湯に入り無病息災を願いながら、寒い冬を乗り切ってきました。
冬至とは、太陽の位置が1年で最も低く、日照時間が最も短くなる日のことです。
冬至は12月21日頃とされていますが、毎年日にちは変わります。今年は、12月22日となります。
夏至の日と冬至の日では、どれくらい日照時間が違うのかと申しますと、なんと東京では約4時間40分もの差があります。
もちろんこれは北半球での話で、南半球では、冬至と夏至の現象が反対になり、日照時間が最も短いのは夏至の日ということになります。
地球上で最も北に位置する北極圏では、冬至の日は、一日中、日が昇らないので、『極夜』と呼ばれています。お昼がない世界、想像できますか。
地球上の場所により、一概に冬至といっても、一様でないことがわかりますね。
■冬至の日がもつ意味
冬至の日を境に、夏至の日に向かって、日一日と日照時間がのびていきます。
このため、中国の太陽暦では、冬至が暦の起点とされました。旧暦が、冬至から暦を計算するのも、同様の理由です。冬至は、太陽が生まれ変わる日と考えられたわけです。
太陽が生まれ変わるという大きな意味をもつ日、冬至の日には、世界各地で様々な儀式が盛大に行われてきましたが、日本も例外ではありませんでした。
東京都新宿区にある穴八幡宮では、江戸時代から続くといわれる「冬至祭」が現在も行われています。
冬至から節分までの期間限定で授与される「一陽来復御守」を求め、冬至の日には鳥居の外まで並ぶほど多くの参拝客が訪れるといいます。
お守りの名前ともなっている「一陽来復(いちようらいふく)」は、冬至をさす言葉でもあります。
冬至の日を太陽の力が一番弱まった日ととらえ、この日を境に再び太陽の力が甦ってくることから、陰の気が極まり、陽の気にかえるという意味で名付けられました。
この意味から、「一陽来復」は、冬が終わり春が来ること。新年が来ること。また、悪いことが続いた後で幸運に向かうこと。の意味でも使われるようになりました。冬至を境に、どんどん運が上昇してくるとも考えられるわけです。
その上昇運にあずかろうと、冬至の日には様々な習わしが生れました。
■世界の冬至
ヨーロッパ北部、スカンジナビア地方などでは、冬至の日は、ほぼ一日太陽がのぼりません。闇が支配している死の神がうろつく日だと考えられ、太陽が再び力を取り戻す日が二度と来ないのではないかと恐れられました。
冬至の前日、太陽が昇るのを見張る係りが選ばれ、山の頂から太陽の最初の光を確認すると、無事に太陽が昇ったことを村中に知らせます。ここから、盛大な祭がスタートします。この祭「ユール」こそが、クリスマスのルーツとも言われていて、現在でも北欧ではクリスマスのことを「ユール」と呼んでいます。
中国北部では、冬至は餃子、夏至は麺を、南部、台湾では、「湯圓」(タンユェン)というお団子を食べます。
湯圓の丸い形は、家族円満を表し、1年丸く収まるという意味があるそうです。
餃子を食べるようになったのは、中国・後漢の時代に、張仲景という有名なお医者さんが、飢えと寒さに苦しんでいる多くの貧しい人々に、餃子を食べさせ、元気にしたという話が多くの人に伝わり、習慣となったようです。
韓国では小豆粥を食べますが、日本同様、赤色は悪いものを追い払うといわれ、1年を無事に過ごせることを願いました。
冬至の日を境に、運気もどんどん上昇するという考えは、新年を目前にとても縁起の良い日のように感じられます。また、新年早々受験シーズンを迎えますので、受験生の皆様には心強い考えですね。
何気なく過ごしがちな冬至の日ですが、意味を知ると、大事な日として迎えられそうな気が致しますね。
■日本の冬至
昔の人々は、冬至の日を「一陽来服(いちようらいふく)の日」とよび、太陽の復活を祝っていました。
「冬至を境に運も上昇する」と考えられているので、長期保存できるかぼちゃを食べて栄養をつけ、体を温めるゆず湯に入り無病息災を願いながら、寒い冬を乗り切ってきました。
■知ってる? 「冬至の七草」

冬至の日には、「ん」のつく食べ物を食べると「運」が呼びこめるといわれています。
夏の季節、土用の丑の日に「う」のつくものを食べて暑い夏を乗り切るのと同様に、縁起かつぎだけでなく、栄養をつけて寒い冬を乗り切るための知恵と考えられています。
・ なんきん:南京、かぼちゃのこと
・ れんこん:蓮根
・ にんじん:人参
・ ぎんなん:銀杏
・ きんかん:金柑
・ かんてん:寒天
・ うんどん:饂飩、うどんのこと
以上、「ん」のつく7つの食べ物は、「冬至の七草」とよばれています。
■冬至の食べ物・「かぼちゃと小豆のいとこ煮」「冬至粥」「こんにゃく」

冬至の食べ物としてよく知られているのが、かぼちゃと小豆を煮た「かぼちゃと小豆のいとこ煮」。
「いとこ煮」とは、主に野菜や豆類でつくる煮物のこと。
栄養価が高く長期保存できるかぼちゃだけでなく、小豆も保存がきき栄養価が高いことから、「かぼちゃのいとこ煮」は、風邪をひかない郷土料理として親しまれています。さらに、小豆の赤い色は「邪気を払う」といわれ、冬至の日、縁起のよいかぼちゃと小豆でつくる「かぼちゃのいとこ煮」が食べられるようになったといわれています。
「冬至粥」も、冬至の食べ物として知られています。お粥に小豆を入れるのが一般的ですが、小豆でなくかぼちゃを入れ「かぼちゃ粥」として食べる地方もあるようです。
日本には古くから、冬至にこんにゃくを食べ、一年にたまった砂(=体に害のあるもの)を体の外に出す「砂払い」という風習もありました。
現在ではあまり聞かなくなりましたが、こんにゃくは、食物繊維を豊富に含む食品として広く知られています。健康維持のためには、冬至に限らず積極的に取り入れたい食材です。
一年でいちばん日が短い冬至。
これからは春に向かって上昇気流に乗るためにも、冬至の食べ物を食べて力をつけましょう!