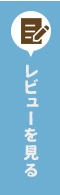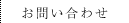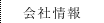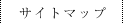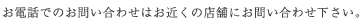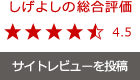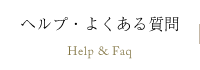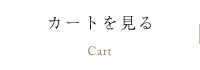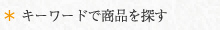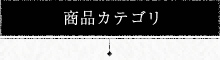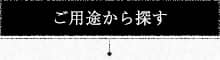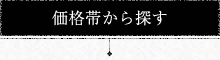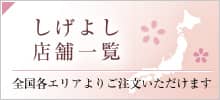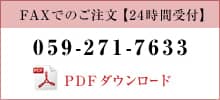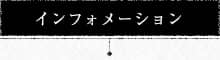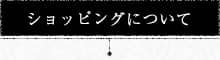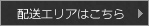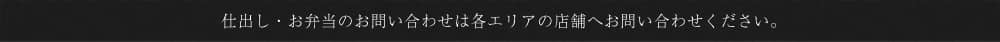2022/07/03

【四季折々】七夕について【しげよし】■7月7日は「七夕」(たなばた)。織姫と彦星の「星」の名前は?
7月7日は、「七夕」(たなばた)。 織姫(おりひめ)さまと彦星(ひこぼし)さまが天の川を渡って1年に1度だけ出会える日で、短冊に願い事を書いて、七夕飾りとして笹竹に飾り付けます。
織姫と彦星はお星さまですが、天文学では、織姫の星は「ベガ」、彦星は「アルタイル」といいます。
夏の時期、日本で良く見える星座は、こと座、わし座、はくちょう座、さそり座、いて座などがあげられますが、織姫の「ベガ」は、こと座にあり、彦星の「アルタイル」はわし座にあります。
織姫のベガと彦星のアルタイルの間に、天の川を渡すように翼を広げたはくちょう座があり、はくちょう座の尾の部分に「デネブ」という明るい星があります。 ベガとアルタイルとデネブの3つの星をつないだ三角形は、「夏の大三角」と呼ばれています。
七夕のお話は、中国古代の民話がもとになっています。織姫と彦星は、中国では織女(しょくじょ)と牽牛(けんぎゅう)。この2つの星は、旧暦の7月7日に天の川をはさんで最も光り輝いていることから、七夕の物語が生まれました。
日本には、奈良時代に宮中儀式として伝わり、「織姫が機(はた)織りの上手な働き者だった」という内容から、手芸や裁縫の上達を願う風習につながりました。 その後仏教が伝わり、お盆を迎えるための準備として7月7日の夜に行われるようになったのが始まりです。平安時代になると、宮中行事として野菜や魚を備えて星を眺め、お香をたいて音楽を奏でたり、詩歌を楽しんだそうです。サトイモの葉にたまった夜つゆを「天の川のしずく」と考え、それで墨を溶かし梶の葉に和歌を詠んで願い事をしました。
江戸時代になると庶民の間にも広まり、梶の葉のかわりに短冊に願いごとを書いて笹竹につるし、星に祈る年中行事に変わっていきました。
■短冊は、なぜ5色? 七夕飾りの意味は?
願いごとを書く短冊の色は、青、赤、黄、白、黒の5色といわれていますが、これは、中国の陰陽五行説〜「木=青・火=赤・土=黄・金=白・水=黒」の5つの要素がこの世のすべての根源である〜から来ています。
■知ってる? 七夕に食べる料理
七夕に食べる料理、知っていますか? イメージがわかない人が多いかもしれませんが、いくつかあるのです。 伝統的なもののひとつが、「索餅(さくべい)」。 唐代の中国から奈良時代に日本に伝わった唐菓子の1つで、小麦粉や餅粉をひねって揚げたお菓子です。 古代中国では、7月7日に亡くなった帝の子が霊鬼神(悪霊)になって熱病を流行らせ、それを鎮めるために好物だった索餅を供えて祀るようになりました。 これが日本にも伝わったようです。
この「索餅(さくべい)」が進化した食べ物がそうめんで、「七夕の日の食べ物」として知られています。 そうめんには色つきのものもあるので、五色の短冊にちなんで「五色そうめん」にすると、七夕らしさが演出できますね。
■七夕にゆかりのある縁結びのパワースポットは?
七夕には、縁結びを願う風習もあります。縁結びや恋愛成就のご利益があるパワースポットを紹介します。
★足利織姫神社(栃木県足利市) 足利織姫神社には、天御鉾命(あめのみほこのみこと)と天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)が祀られています。天八千々姫命は、一説には織姫を指すとも言われているそう。足利織姫神社は縁結びのご利益があり、縁結びの神様として「恋人の聖地」になっています。
★機物神社(大阪府交野市) 機物神社には、4人の神様が祀られているといわれています。その中の天棚機比売大神(あまのたなばたひめおおかみ)は、「織姫神(おりひめのかみ)」を指すと言われており、恋愛成就・子宝・安産などのご利益があるようす 7月には、境内は笹でいっぱいになり、願いを込めた短冊が飾られます。
★七夕神社(福岡県小郡市) 七夕神社には、織姫神(おりひめのかみ)と媛社神(ひめこそのかみ)が祀られており、古くから女性の信仰を集めてきました。神社の近くに流れる宝満川を天の川と見立て、対岸にある老松宮には、牽牛(げんぎゅう=彦星)を祀っています。 まさに「七夕にまつわる神社」といえる神社です。
家族や恋人と、季節行事・七夕を楽しみましょう! |